CEFRとは
外国語教育や日本語教育や従事する人であれば、CEFRという言葉くらい聞いたことがあるはずです。しかしその内容を簡単に説明せよ!と言われてできるでしょうか?もちろん私も説明できない一人だったので、本書を手に取りました。
しかし、CEFRを一言でいうことは難しいですね。以前は「CAN DO リストじゃないの?」くらいに思っていましたが、そんなに生易しいものでないものがわかります。ある意味CEFRは哲学であり、思想です。今後我々がどうやって母語を同じくしない人々と同調して生きていくかを真剣に考えた一つの地図のようなものではないでしょうか。
複言語主義
CEFRを語る上で外すことができないキーワードが「複言語主義」でしょう。これは「多言語主義」と比較するとよくわかります。
「多言語主義」は複数の外国語能力が「横並びに共存していること」(p12)です。私は日常生活において「日本語」「韓国語」「英語」を用いますが、日本語の実力を10とするなら、韓国語は8、英語は3といったところでしょうか。このようにそれぞれの言語が独立して存在していると認識することを「多言語主義」というようです。
一方の「複言語主義」は横並びではなく、私の内部に「日本語」「韓国語」「英語」が共存しているという状態を指します。場面に応じてすべての言語能力を駆使して、日常における言語コミュニケーションを遂行しているのです。
例えば、「ある人からSNS経由で英語のメッセージをもらった」という状況を想像してみてください。これからなすべきことは、そのメッセージに返信することです。まずはその英語のメッセージを読みます。その時私は英語の読解能力を駆使します。そして返信をするわけですが、メッセージをやり取りする相手は高度な韓国語能力を持っていることを知っています。私は英語で文章を書くよりも韓国語で書くことのほうが得意なので、韓国語でメッセージに返答します。
私は「メッセージに適切に返答する」というタスクをこなすことに成功しました。英語と韓国語能力を駆使したわけですが、どちらにせよ目的を達成できたことに変わりはありません。複言語主義とは「目的を持ったコミュニケーションを実現するために重要な役割を持つのが複言語能力であるとし、その能力の育成を言語教育の目的とする考え方」(p10)なのです。
「多言語主義」的に言うと、私は英語の文章作成能力が低いのでこれを鍛えなければならないということになります。つまり、先述しましたが、それぞれの言語能力をそれぞれ独立したものとして見るということです。
肯定的な思想
こういうのを見ると何となく肯定的な感じがしませんか?
本書でも言及されていますが、CEFRの考え方は減点方式ではなくて、加点方式のようです。「~ができない」じゃなくて、「~ができる」を積み上げて行こうというんですね。外国語で「できないこと」を数えていったらキリがありません。世の中には無数のコミュニケーションがあるわけですから。だったら「~ができない」よりも「~ができる」を
数えた方がいいですよね。
CEFRでは母語話者も外国語学習者と分けて考えないという立場を取ります。これも素敵な考え方です。これまでは母語話者は絶対権力の持ち主だったわけですから。
母語話者だって、できないこともあります。私は企業で働いたことがないのでサラリーマンの常識的なものは少なからず欠如していると思います。「ビジネス関連のメールを書け」と言われてもその業界の慣例や常識をしっかりと抑えたメールをすぐには書けないでしょう。
一方日本でビジネスをしている外国の人なら経験が豊富ですからすぐに書けるかもしれません。テンプレートなんかも持っているかもしれませんしね。このように「あるコミュニケーションを達成する」能力は必ずしも母語話者が優れているかどうかはわかりませんし、両者を分けて考える必要もないでしょう。
CEFRに対する誤解
私を含めた不勉強な日本語教師はCEFRに対して誤解をしている部分があるかもしれません。
まず、「CEFRはヨーロッパの言語を対象としたものでしょう?」というのがありがちな誤解。違います。これが提起されたのはヨーロッパですが対象となる言語としては、ヨーロッパで使われている・学ばれている全ての言語ですから当然日本語も含まれます。
また、CEFRはあくまでも「リファレンス(参照)」であり、「スタンダード(基準・規範)」ではありません。だから「これが絶対!」というわけではないんですね。そういうポジションです。
「ま、とりあえずこういうくらいでレベルわけして示しとくから、参考にしてちょ」みたいな軽いノリなんですね。だからもっというと「CEFR至上主義」みたいな教師がいたとしたらこの教師はCEFRの理念を理解していない、という皮肉になってしまうわけです。
授業を変えていこう!
本書はCEFRに対する質問に答える、という形でCEFRとは何かを非常に簡潔に説明した本です。簡潔ですから理解は進むのですが、「じゃ、明日からどうしようか」となると困惑する教師も多いでしょう。そのため後ろの方ではCEFRの理念に基づいた授業設計についても紹介されています。
授業案を見ればわかりますが、既存の授業とそれほど変わるところはありません。だって「みんなの日本語」を用いた授業案とかが紹介されているんですから。
恐れる必要はないんですよね。「おわりに」でも書かれていますが、「今使っている教科書の見方をほんの少し変えるだけで、CEFRの実践につなげることができます」(p173)。要は、「~ができるようになる」という大きな目標があって、「では、~ができるようになるためには、どんな練習が必要か」を真剣に考えていくことなんですね。
今までは漫然におこなっていた教室活動をどのように変えていくか、そのためのヒントが満載の良書です。
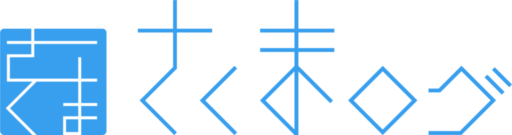



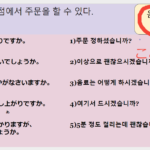

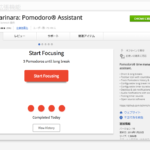
ピンバック: 【レビュー】『フォーカス・オン・フォームとCLILの英語授業』 – さくまログ
ピンバック: レビュー『バイリンガルの世界へようこそ』上 | さくまログ
ピンバック: カルチャーマップから考える日本語教育 その3 説得 | さくまログ