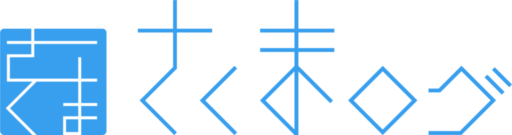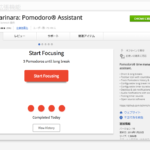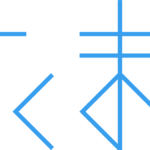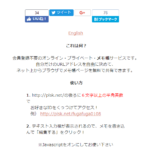アマゾンの「内容紹介」より
外国に対し、「日本のマネばかり」「石油が出るだけのラッキーな国」と上から目線を続ける日本の”グローバルエリート”。中国、韓国、そしてドバイでさまざまな外国人と交流を持つ現役外交官が本気で警鐘を鳴らす。
著者は現在、韓国・釜山の日本領事館総領事です。私も釜山在住なんですが、ひょんなことから著者に接触する機会を持ちました。こんな機会はあまりないと思い、予習のつもりで読んでみました。いや~なかなかおもしろかったです。
「町のネズミ」と「田舎のネズミ」
著者は近年、日本、韓国、中国、UAEで勤務してたそうです。その4つの国での滞在・実務経験から「日本ちょっとやばいんじゃない?」と思うに至り、それを文章化した、という感じの本です。確かにこの本を読めば「日本のちょいヤバ」な感じはわかる気がします。
以下ハイライトした部分を中心に(カッコ内の数字はKINDLEでの位置です)。
中東も中国も韓国も、日本よりはるかに積極的に外から学び、新しい世界に適応しようと必死に努力している。日本は外から学ぶ姿勢が衰え、ダイナミズムを失う道にすでに入り込んでいるように見える。(1699)
↑このあたりが本書の中心内容です。これは短い期間のうちに数カ国でローカルの濃密な空気間を味わった人じゃないとなかなかわからないかもしれません。実際私は韓国に10年以上いますが、韓国の空気感はわかっても日本の空気感はよくわかりません。この視点は外交官ならではでしょう。
日本は国内市場がある程度大きいことがアダになっている。国内が居心地良いから若手が(留学も赴任も) 外に出ないし家族がいやがる。英語も熱心にならない──それはそうだとしても、何の弁解にもならない。国際社会が日本にハンデをくれるわけではない。国のダイナミズムを損ない、視野を狭めてよい理由、国際化を怠ってよい理由にはならない。(1717)
↑その理由はこれ。同意できます。まあ世界に出なくてもそこそこ食っていけますからね。英語できなくても全然困らないですしね。
世界からみれば、日本はグローバリゼーションに距離を置き、あまり適応努力をしていない。だが日本人の多くは「グローバリゼーションに過剰適応した」、「自分は町のネズミでありすぎる」と思っている。中東や中韓から「田舎」に見えるとは夢にも思っていない。(1793)
やや厳しくいえば、「上から目線で他国を見下している間に、自分が遅れてしまった。世界認識もズレてきた」という話だ。(2463)
↑これはありますね。私もその一人かも(笑)。著者はうまい例えをしていますね。そう日本はもう「町のネズミ」ではないのです。そういう現状認識をしっかりとした上で、著者の主張は、
国力をもっと重視し、外国との競争でもっとしっかりたたかうべし、教育を強化すべしという話をした。同時に、日本は外国なしには生きていけない、独善と偏狭、ごう慢な「上から目線」では日本は沈むとも書いた。中韓や中東の欠点だけ見て安心しているような甘い日本では思いやられるとも述べた。(2502)
↑ということです。「国力をもっと重視する」とかいうとすぐに軍事力とか戦争のことと結びつけてしまう人もいますが、そういういわゆる「右翼的な思想」とは違います。政治や外交の話になるとすぐに「右」とか「左」とかいう話になりますが、本書はそれとは違います。ただ、周りが努力しているのに一人それを怠ると、バスに乗り遅れるぞ!ということです。
これは「日本語」で飯を食っている人間にとっては無視できない問題です。我々日本語教師が飯を食って行けているのは「日本」というブランドのためです。なぜ英語がグローバルな言語になったかというと、イギリスやアメリカが世界の覇権を握ったからでしょう。それと同じです。
これからも安定的に日本語学習者を供給してもらうためには日本のエリートたちにがんばってもらわねばなりません(他力本願)。
のんびり暮らしたい世代
先日もホンジュラスの日本語学習者の人と話をしたのですが、「私の町には日本人はいません。韓国人はけっこういます。」と言っていました。どうして?と聞くと、「韓国の工場がある」とのことでした。
もちろん、「ある国や地域に工場があるかどうか」で国力や経済力が測れるとは思いませんが、この本を読んだ直後のことだったので、やはりな~と思うところはありました。
著者の状況分析や主張には反発の余地がありません。まさにそのとおりだと思います。ですが、「なぜ日本がこうなったか」を考えると「同情の余地がある」とも言えると思います。
例えば私の父は1948年生まれです。いわゆる団塊の世代です。その団塊の世代の子供世代である我々(私は1979年生まれ)は父母が身を粉にして働いてきたのを見てきました。その世代の男のほとんどは「会社人間」だったことでしょう。その結果私などは何不自由することなく育ってきました。最近では老害だの何だの言われますが、その世代へのリスペクトの思いは常に持っています。
ただ、その反発でしょうか。金はもういいから、家族と遊んだり、趣味を持ったりして自由気ままに過ごしたい!と思うようになりました。それが我々の世代でしょう。
もう少し上の年齢(現在40代後半くらい?)になるとバブル期を知っていたりして、ちょっと違うのですが、ともかく私の前後の世代は大学卒業時は「就職氷河期」でしたし、基本的に好景気の空気をあまり知らないんですよね。だから「過去の栄光を!」ともなりませんし、まあ、のんびり行こうぜ!となるわけです。
ただ、国を動かすような一部のエリートにはがんばってもらわないといけませんね(他力)。
グローバリゼーションはオプションではない
それと、おもしろかったのがこの部分です。
グローバリゼーションとは、現代の世界史で大きな動向、潮流であり、「思想」やだれかの「思惑」というものではない。世界各国が置かれた環境の変化、ないし半ば、国際社会のゲームのルールの変化という面がある。(1346)
しかし、著者が違和感を感じるのは日本でのこの「グローバリゼーションの捉え方」です。
これが世界大の環境の変化であるのに、選択すべき「 思想」「オプション」の一つであるかのように、これを「拒否、忌避」しようという姿勢が一部に見える(1349)
↑この部分を読んだときは膝を打ちましたよ。そうなんですね。こういう「時代の流れ」っていうのは選択、オプションではないんですね。
もう少し具体的な例を出すと、グローバリゼーションを下支えしているICTの導入というのももうオプションではなくなってきています。「私はアナログ派だから」とかはもう通じないはずなんです。個人的にアナログ志向であるのは構いませんけど、それは自分の中で解消すべき問題です。
私達は否応なく「現代社会」という場に投入されているわけですから、その場には逆らわずルールに則って生きていかないといけませんね。
私は別にエリートではありませんが、昨今の日本の世界での位置づけのようなもの知ることができて、目から鱗の一冊でした。