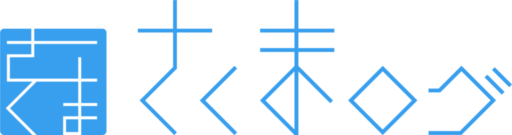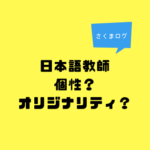今回Twitter経由で、@aya_nihongoさんが主催する「教育アプリ体験会」に参加してきました。↓
✨教育アプリのワークショップ✨
— Aya (@aya_nihongo) February 11, 2019
今回のアプリは、以前紹介した【Socrative】です。
新しいアプリを
オンラインで集まって、一緒に試してみませんか💡
日時: 2/16 (土) 10-11時am
参加費:無料
あと数名の方、ご参加いただけます〜!
オンラインからお申し込みもできますよ👍#ICT教育 #日本語教育 pic.twitter.com/G6B9l8R0Rm
Socrativeに関する紹介ビデオはこちら(これも@aya_nihonogoさんのですね)。
Socrativeって何?
アプリの概略の説明をしようと思いましたが、↑のYoutube動画を見てもらったほうが全然早いですね(笑)追加で私が説明すべきことはほとんどありません。
動画の中でも説明されていますが、私もKahoot!を使用していました。基本的にできることはSocrativeとKahoot!でほぼ同じなんですが(動画の指摘にもあるようにKahoot!のほうがカジュアルであるという点は別として)、Scrativeの方が細かい設定が可能なように思えます。
【Kahoot!関連の過去の記事】
■Kahoot!を日本語授業で使ってみた
■Kahoot!のオプション日本語訳!
ざっくり言うと、Kahoot!は、「クイズ大会」用のツール、一方のSocrativeは「学び」用のツールと考えることができるのではないかと思います。ですから、それぞれの設定も前者は「クイズ大会を盛り上げる」ための設定が多いように感じます(得点ボーナスをどのように与えるか、等)。
Socrativeは学び用のツールですから、やはりそれに特化しています。Kahoot!では選択問題しか提示できませんが、Socrativeは記述式問題も組み込むことができます。また、教師用の方、つまり教室でスライドで学生に見せる方の画面では学生の名前を非表示にするとか、そういったことも可能です。
「体験会」の意義
今回の体験会は主催者と私も含めて6名が参加しました。1時間の体験会でしたが、概要の説明→参加者自ら問題の作成→参加者間で問題のやり合いっこという流れで、なかなか濃密な時間でした(接続を切った後に、「うーん、よくわかった」という独り言が出ました)。
こういったツールを一人で練習する場合、一人で学生用と教師用の画面を交互に見ながらやらないといけないので大変です。「教師(学生)からはこう見えるのか」というのをいちいち確認しないといけないわけです。
それが、この体験会では「問題のやり合いっこ」などがあって、学生側の視点、教師側の視点どちらにも立てるので感覚的に理解ができました。
以前のことですが、暗記用のツールとして有名なQuizletの機能の一つとしてQuizlet Liveというのがあってクイズ大会の団体戦みたいなことができます。これを授業で使おうと思って使い方を調べていたんですが、学生が4人以上登録しないとゲームが始められないんですね。そこで私は家中にあるスマートデバイスをかき集めて予行練習をやったという苦い思い出もあります(Kahoot!にはデモ機能もあるんですが、Quizletにはなかった)。
そういった意味で、今回の体験会は非常に濃密な一時間でした。ありがとうございました。私もいずれ何か還元できるように頑張りたいと思います。