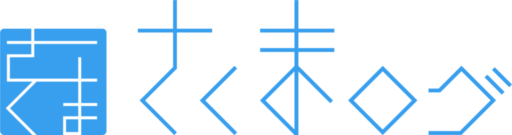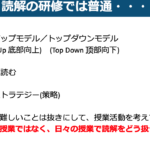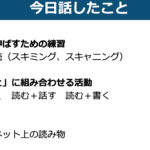下の記事を先にご覧いただけると、これからの話がわかりやすくなると思います。
■グーグルクラスルームでN1を目指す!N1 Project 始めました。
まあ簡単に上の内容を要約しますと、非ネイティブの日本語講師を対象にN1合格を目指す自律学習型のプロジェクトをおこなった、ということです。Google系のツールを駆使して、できるだけ双方(私と講師陣)の負担を少なくし、スキマ時間を使って日本語能力向上を目指します。
上の記事を書いたのは2019年の5月なのですが、「その後どうなったのか?」というお問い合わせをちらほら頂いていました。今日はそのN1プロジェクト!のその後について書きます。
結果
まず、結果ですが、
N1合格者は出ていません。
ただ、私に弁明をさせてください(笑) 私たちがこのプロジェクトをはじめてから、このプロジェクトの受講者の中でJLPTを受験した講師は一人もいないのです(あ、一名いましたがそれはProject開始直後でしたので勘定に含めていません)。なぜかと言いますと、2020年は私の住むカンボジアでは2回ともJLPTが中止になってしまったからです。2019年12月におこなわれたJLPTが直近のものなんですが、その回にN1を受けた人は一人もいなかったのです(受験をしなかったのは人それぞれ理由が違いますが)。
受験しなかったとは言え、2019年5月から1年ほどは緩やかにN1Project!自体を実施はしていました。ただ2020年度に入ってからは、例のCovid19の影響で職場もいろいろバタバタしてきました。対面授業が禁止になったり、テレワークになったりもしたんですが、オンラインで集まったりしてほそぼそと続けてきました。しかし結局、参加者の先生たちが他の仕事に忙殺されるようになり、2020年5月に一時中止を宣言しました。
というわけで、
・N1を受けた人は一人もいない
・1年ほど続けたが、現在は動いていない
というのがN1Project!の途中結果報告です。
しかし、目に見える結果が出ていないとは言え、1年近く断続的に続けてきたわけですから、こちらの側にもこのプロジェクトをしながらわかったことがいくつかあります。ここからはそのやり方の反省やまとめをおこないます。
Googleクラスルームの使用
これは良かったと思います。投稿予約などもできますし、だれが課題を出したかどうかというのがひと目でわかります。別に成績をつける必要があるわけではないんですが、出したかどうかだけを見ていても、参加者のプロジェクトへの関心度合いがひと目でわかります。
参加者は10人以下ですのでTelegramやLINEみたいなツールを使っても管理はできると思いますが、やはり課題中心となるとGoogleクラスルームは便利ですね。
日本語の森の利用
文法や語彙の問題を解いたあとのフィードバックは日本語の森を利用しました。というよりも、日本語の森で解説されている部分を問題にしていたので、そのビデオはフィードバックとしてはばっちり、ということになります。ただ、参加者の中からは、
ビデオを見てもよくわからない部分がある
という指摘を受けました。まあそれはそうですよね。もちろん日本語の森が独習者にとって非常に役に立つものであることに変わりはありませんけど、一方通行のメディアですし、直接法ですので、参加者が十全な理解を得られないこともあるでしょう。
ネイティブ講師の参加
また、だんだんやり方がマンネリ化してきたこともあったので、少しやり方を変えようと思いました。他の先生たちに意見を募ったところ、
問題の解説をネイティブの先生がしたらどうか
という提案を受けました。できるだけ人力を使わず楽をしようと思っていたわけですが、少し負担を負うことにしました。ただ、全部の問題についてネイティブの先生の解説をおこなおうとすると、授業準備と変わらない負担になってしまうのでそれは避けたいと思いました。
ですので、週に1問だけ文法問題のうちの一つをネイティブの先生に授業形式で解説してもらう形をとることにしました。ちなみに当時はネイティブの先生が2名でしたので、文法問題全5問のうちの2問について解説が入る、ということになります。
この形式でおこなったのは、実は長期中止に入る前の一回だけだったのですが、私としては
悪くない
と思いました。もちろんそれはネイティブの先生の負担の下に成り立つわけですが、N1レベルの文法問題を週に一度解説するくらいならそれほど負担にはならないはずです。また、私たちの機関にはN1レベルのクラスはありませんので、先生たちにとっても上級文法の教え方にふれるいい機会になると考えました。
またこのN1プロジェクトは、課題をそれぞれが締め切りまでに解いておいて、その後決められた日時に集まって50分ほど復習をするという体裁だったんですけど、裏の目的としては職場の人間関係の形成、というのもありました。日本語教師はどこでもそうですけど、普通授業は一人でしますし、授業準備も一人でします。なので孤立しようと思えば簡単に孤立できるんですよね。
ただ、やはり仕事をする上では「協働する」というのもやり甲斐を感じる部分ですので、「協働する」下地を作るためにも定期的な集まりは必要だと思います。それが「勉強会」という形で実現できるのは教育機関としては理想の形ではないでしょうか。
Quizletの利用
50分のリアルタイムセッションでは、課題についてのフィードバックをおこなうんですけど、Quizletを多様しました。例えば、語彙の問題は毎週10問ずつ課していたのですが、それを毎週Quizletに入れます。そして毎週のセッションの始まりにはランダムでそのフラッシュカード見ることにしました。
毎週10問ずつ追加されるわけですから、結構な量ですよね。10週やれば100こです。もちろん限られた時間で毎時間それを復習することはできませんから、ランダムで15問だけ毎週やってみようとしたんですね。
…私の言っていること、よくわかりませんよね。まあ、理解すべきことは、参加者は「毎週10問語彙問題をとく」んですけど、それを毎週Quizletに追加していったということです。そしてそれを毎週毎週ランダムで解いてみるというのも並行しておこなった、ということです(まだわからないけど、もしちゃんと理解したい人はメッセージをください)。
ちなみに少しずつ追加していたQuizletは↓になります(はじめにひらがなが見えると思いますが、使い方としては逆で、先に漢字の文章を読みます)。
まとめ
というわけで、志半ばで止まっているN1 Project!について途中報告をしました。まだまだあきらめたわけではありません。今はちょっと機関自体が忙しい時期ですので、それが終わって3月か4月くらいからまたN1Project! ネクストシーズンを始める予定でいます。
ただ、一つ思うのは、N1対策と言いつつも実際にどういう問題が出ているのかがわからないので、やっている対策が本当に対策になっているのだろうか、という迷いです。
だったら、多読的な方向に進むのがいいんじゃないかと思ったりしています。教材ではなくて、生の文章を読むということですね。しかも読んでおもしろいものを。ただそうなると、コンテンツ選びが非常に難しいです。N3くらいだと多読教材なんか出ているんですけどね。
そう考えて「短くまとまっていて、読み物として面白く、かつ高校生くらいで読めるような本」を探しています。
一つ思いついて購入したのは↓です。河合隼雄先生の短かいけれども金言あふれる文章ですね。ただ、私は購入前には「短い」と思っていたんですけど、実際日本語学習者に読ませるとなると結構長いような気もするんですよね。
あとは、最近読んだ「アウトプット大全」や「インプット大全」なんかも短くていいかな、と思っています。おもしろいところをピックアップしてもいいですしね。
■効果的なインプットとは?
■レビュー『学びを結果に変える アウトプット大全』
あと読解対策には↓がど真ん中ストライクかな、と思っています。
まあ、他にもアイディアはあるんですが、なんか考えてたら楽しくなってきました(笑) また今年の間にはこの進捗状況をご報告できるかもしれません。とりあえず3月か4月の再開に向けて!コメントなどもいただけたら嬉しいです。