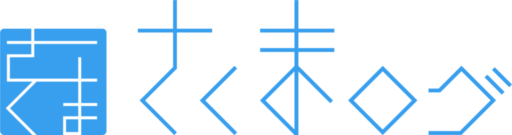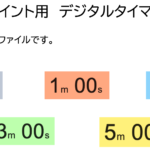■『私たちはどう学んでいるのか』①スキルとしての言語
■『私たちはどう学んでいるのか』②基礎から応用?
↑からの続き。今回は最終回となります。↓の本を読んで考えたことをつらつらと書いています。
鈴木宏明(2022)『私たちはどう学んでいるのか―創発から見る認知の変化』筑摩書房
「スモールステップ」を問い直す
私が面白いなと思ったのは「スモールステップ」式の教育に本書が疑問を投げかけているところです。一応スモールステップについて引用しておきますと、以下のようなことですね。
きっちり教えるという話になると、よく出てくるのはスモールステップという考え方である。つまり教えることを要素に分解し、それを基礎的なものから順に並べ、次にそれらを組み合わせた複雑なものを設定することを繰り返していくというものである。また、各々のステップでテストを行い、そのステップでの学習事項が十分に習得されたかどうかをチェックする。そしてそのチェックを通れば次のステップに進む。(pp.153-154)
まさにこれは日本語教育ですね。文型積み上げ式の教育がわかりやすいと思いますが、まずは名詞文→形容詞文→動詞文ときて、ます形→て形→た形・・・みたいな形で学習が進んでいきます。そしてやっぱり途中で到達度テストがあったりするのも同じですね。
まあ語学教育の世界ではアプローチが違っても多かれ少なかれスモールステップ式になるのが普通です。でも普通すぎて私たちがあまりそこに注目をしていないというのも事実ですよね。本書でスモールステップの弊害として指摘しているのは↓のようなことです。
要素分解して、個々のスキルや能力を鍛えていけば、最終的にはちゃんとした学習がなされるという話は成立しない(p.155)
本書では「風邪」の例が出されています。人為的に風邪の症状(発熱、鼻水、咳など)を発生させることはできるけど、発熱があって、鼻水や咳が出ているからと言ってその人が風邪をひいているとは言えないというような例です。
外国語教育に寄せて考えますと、「初級文法や語彙を一通り習ったとしても、それを使ってコミュニケーションできるかどうかはまた別」といったところでしょう。例えば日本の公教育における英語とかはその典型かもしれません。
兆候と原因
もうちょっとそれについて考えていきましょう。
素晴らしい能力を持った人がXができる、Yができる、Zができるというのは、全部兆候なのである。兆候は原因ではない。兆候を真似させても、原因が成立するとは限らないのだ。 (p.156)
ここで言う「兆候」を「高い語彙・文法力」、「原因」を「高い言語運用力」と置き換えればわかりやすい。語彙力や文法力があって、例えば能動文を瞬時のうちに使役受け身に変えることができるとか、紛らわしい自動詞と他動詞を全部記憶しているとか、まあそれはそれで素晴らしいことなんですけど、そういう「高い語彙力や文法力」を持っている人が必ず日本語で高いコミュニケーション能力を持っているとは限らないということですね。
結果的に、「高い言語運用能力」を持っている人は同時に「高い語彙・文法力」を持っているでしょうけど、私たちが教育で養成すべきは「高い言語運用能力」であって、「高い語彙・文法力」ではないということです。
今私たちの職場では中国の中等教育で日本語を教える、特に経験が浅い教師を対象に研修をおこなっています。中国では近年日本語を外国語として選択する中高生が増えているんですよね。その背景には「英語で大学受験するより効率的に点数が取れるから」ということがあるみたい(もちろん他の理由もある)なんです。
で、そうなると多くの先生たちの目標は「生徒に日本語の試験で良い点を取らせる」ということになります。だから「効率よく試験で高得点を取らせるためにはどうしたらいいか」を考えることになります。もちろんそれはそれでいいと思いますが、研修を提供する私たちが一貫して取り続けている姿勢は、
運用力を上げることがテストの点数を上げることにつながる
ということなんです。
このあたりを本書では「遠隔項」「近接項」というようなちょっと難しめの語彙を使って説明しています。詳しく知りたい方は読んでみてください。
準拠枠と参照枠
この話はたまたま読んでいた別の本にも出てきました。
この第1章に日本語教師の専門性についての考え方が書いてありました。ちょっと話が長くなるので簡略化しますが、例えば「日本語教師が持つべき専門性・知識リスト」があったとして(あるんですが)、それを準拠枠として見るか参照枠としてみるかという点で全く違う捉え方があるとしています。
簡単に言うと、準拠枠として捉えるというのは、「ふむふむ日本語教師に必要な要素はこれか。私の場合は大体全部満たしているから日本語教師としては問題ないな。ただこの項目だけは弱いから、今度はこういった研修を受けようか」という捉え方。本書では「一般的・静態的専門性観」と言っています。
一方で参照枠として捉える、というのは「専門性は個々の教師によって異なり、各々が自らの実践を通して作り上げていくというプロセス(p14)」であると書かれてあり、専門性・知識のリストをあくまでも参考にしつつ「私は日本語教師として何をすべきか、どうあるべきか」を対話的に構成し続けていくプロセス(p17)」として捉えるとしています。そしてそれを「個別的・動態的専門性観」と言っています。
言うまでもなく「準拠枠」として捉える専門性観は「兆候」を整えることを重視することによって養われ、一方の「参照枠」的に捉える専門性観は「原因」を自ら追求していくことによって養われるものです。リストの参照枠的な捉え方が望ましいと考えられるのは言うまでもないでしょう。
「原因」を育てるために
そして話は戻る。本書では↓のように言っています。
チェックリストなどの「きちんと教える」教育は、やっている方も受けている方もなんとなく満足する。「ここまでやった」、「ここをクリア」、「次の課題はなんだ」などという雰囲気に浸れる。しかし、これは「教育ごっこ」に陥る危険性は高いと思う。(p163)
しかし、じゃあどうしたらいいんでしょうか。
本書では、「兆候」ではなく「原因」を模倣することが大事だと言って、伝統芸能における住み込みの内弟子と師匠の話などがでてきます。
言語教育で言うと、「原因」を模倣するということは結局
実戦経験を積む
ということになると思います。文法の説明や、入れ替え練習だけをやっていては「兆候」を模倣するだけに終わってしまうんですよね。ですから実戦経験を積む必要があるでしょう。できるだけ自然な条件下で自然な言語運用が求められるような活動をたくさんさせましょう、そしてその経験の中で自分なりに法則を見出したり、スタイルを育て上げ、自分なりのコミュニケーションが取れるだけの言語運用力が身についていく・・・
誤解のないように言っておきますが、これは文型積み上げがだめとかそういう話ではありません。どういうアプローチを取ろうとも、それが実際の言語使用に裏打ちされたものでなければ結果的に「兆候」の模倣に終わってしまい、それでは真の言語運用能力は育たないという話です。
まとめ
というわけで3回にわたって、「私たちはどう学んでいるのか―創発から見る認知の変化」を下敷きにして言いたいことを言ってきました。3回に渡って書いたわりには、結論が、
実戦練習をたくさんせよ
という当たり前の話になってしまい、すまない(笑)、でもなんかあれですね、結論とか考えずにつらつら書いてきましたけど、割と最近よく言われるような話になっているのではないかと思いますね。
最後に本書からの引用を一つ。
教師自身がそうでなくてもよいだろう。人類史の中には偉人、素晴らしい発見、美しい理論がいくらでもある。世界には、不思議なこと、克服しなければならない問題、そうしたものはいくらでも存在する。それらの助けを借りつつ、学習者たちに小手先のやり方や単なる事実=近接項を伝えるのではなく、その先にあるもの=遠隔項に向かわせる、そうした目線の高い姿こそが学習者に棲み込みを通した知識の構築を促すのだ。このためには教師自身が探求を愛する探求者そのものでなくてはならないし、遠くを見据えなければならない。(p170)
ここまで読んで私はやっと気づいたいんですが、本書は「どこを見るか」という話だったのです。
教育者としてどこを見るか、どこを目指すか、目指させるか、そういうことなんですね。
もちろん日々の授業は「なになにという教科書の読解パートを担当する」と言うことになったとしても、その先には何があるのかを考えて、遠くを考えて教育全体を考えていかないとだめだということですね。
とりあえず今日からできることは、目線を1メートルだけでも後ろにずらすことかもしれません。
大変勉強になりました。
■『私たちはどう学んでいるのか』①スキルとしての言語
■『私たちはどう学んでいるのか』②基礎から応用?