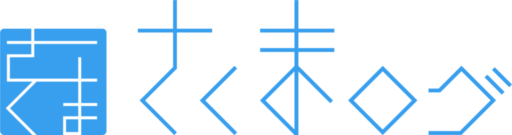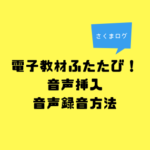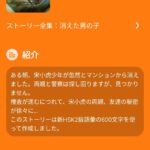何気なく書いた↑の記事ですが、予想以上に反響が大きくてびっくりしました。やはり「日本語教師と大学院」は切っても切れない関係なんですね。今回はいただいた反応をもとに、前回書ききれなかったことを少し補足する形で書いて行こうと思います。
資格としての修士
前の記事で、私は内実を求めてというよりはライセンスとしての側面から大学院に行ったということを書きましたが、やはりそういう人は多いみたいですね。
大学院進学を決めた理由は、もう20年以上も前の事なので忘れました。たぶん
— 🌹ばらじゅん ̄🇹🇭 (@barajun) September 1, 2020
1.タイで2年間教えて、タイ語について研究したいと思った
2.タイの大学で専任講師として採用されたい!(専任になると、給料が約4倍になった)
修士号があれば、専任になれるので、博士号の取得は全く考えませんでした。
大学3年生の私に読ませたかったなぁ…。
— Tomoko Kuroda / やさしい日本語アドバイザー (@bloomyourwish) September 1, 2020
ぬくぬくするために佐久間先生が考えて行動してきた軌跡を読める今の大学生が羨ましいなぁ…笑
大学院で研究したい!!!って進学する人の方が珍しい気がするのは私のまわりだけですかね…。
理系も就職のことを考えて大学院に行くイメージがあります。
わーきっかけ同じです!
— いちほい🍒🌥️🐾🐶+-3kg (@ichgohoippu) August 31, 2020
違うのは日本で修士に行った事と落ちこぼれだったことです😥
とにかく院進学に悩める子羊の方は必見よ☝️ https://t.co/5v3s2mlWFp
日本語教育関係者は「日本語教師」としてのアイデンティティが強い人と、「研究者」としてのアイデンティティが強い人に分かれると思いますが、おそらく私のブログを読んだりツイッターでフォローしてくれているのは「日本語教師型」が多いからかもしれません。
「研究者型」の日本語教育関係者の中には「純粋に研究がしたかった」「良い論文を書いて教授になりたかった」という人もいると思います。
私は学部でも日本語教育学を専攻しましたが、学部からストレートで院に進んだ人の顔ぶれを思い出しますと、「就職に有利だから院にいっとこ」という感じの人はいなかったような気がします。
始まりが半分
院に行くか行かないか、ってかなり迷うと思うんですよね。私も同じでした。終わってみたら何てことはないわけですが、学費のこと、仕事や家庭との両立、終わった後のリターンの見込みなどを考えるとなかなか踏み出せない気持ちもわかります。
また海外にいる場合に結構面倒なのが書類集めなんですよね。大学の卒業証明書とか、成績証明書、指導教官の推薦書など。うわ、思い出すだけでも憂鬱な気持ちになります。
私が修士に入った2000年代では、大学関係の証明書はすべて郵送でした。今は変わっているかも知れませんが、日本の実家の両親にお願いして転送してもらった記憶があります。また国際郵便で往復封筒を大学時代の教授に送って、しっかりと封がされた推薦書を送り返してもらった記憶があります。
あ、ですから学部にしても大学院にしても指導教官と良い関係を保っていくことはとても必要なことです。私の場合は学部、修士、博士すべての過程においてナイスな先生ばかりでしたので、そのへんのストレスはなかったですけどね。
大学院のことを考えないわけではありませんが、やはり家事育児仕事と大学院の両立、年齢や体力も考えると早い方がいいんだろうなぁと頭では理解できます。
— Tomoko Kuroda / やさしい日本語アドバイザー (@bloomyourwish) September 1, 2020
が、なかなか決めきれないところがあります。
踏ん切り、必要だと思います。
踏ん切り、必要なんですよね。本当に。
私の場合、修士の時は独身だったからそれほど葛藤はなかったんですが、博士に入る時、第一子が3歳そしてその1年後に第二子が生まれたので、忙しさは半端なかったです。共働きでしたしね。
第二子の予定日のちょっと前に地方で学会があったんですけど、「もし妻が産気づいたり出産が早まったら発表とりやめにしますのでヨロシク」という話を学会の事務局にしていたことを思い出しました。
子供の送り迎えは私がやっていましたし、子供が家にいる時(起きている時)は仕事および勉強は一切しないという鉄の掟を守っていましたから、毎日4時とかに起きて勉強したり、論文を書いていました。
今思うとすごい生活だったな、と思うんですが、そこから導出された結論が2つあります。
・縛り(特に家庭関連)が多いと作業の効率性が高まる&計画性が備わる。
・まあ、どうにかなる。
韓国のことわざに「始まりは半分」というものがあります。スタートさえ切れれば作業の半分は終わっている、ということですね。割とこのことわざが好きです。
大学院は勢いで!?
フルタイムの仕事しながら大学院とか、子育てしながら大学院とかそもそもが酔狂な話なんですよね。だからこそ踏ん切りが必要だし、思い切りが必要だと思います。しかしそれは入ってからも同じです。
私は修士を最短の2年で終えたんですけど、私の所属していたところでは「最短で終える人もいるにはいるけど、ちょっとオーバーする人の方が多い」という話でした。私もやはり誘惑がありました。「半年伸ばそうか」という。
でも一度伸ばしたらずるずる行くんじゃないか、というのもあって誘惑に負けずに終わらせました。勢いって大事だと思うんですよね。あと純粋に、時間が経ったり、空白ができると、内容を忘れちゃうんですよね。例えば今自分の書いた過去の論文とか読むと、「本当にこれは自分が書いたのか?」って思ったりします。「すげーな過去の自分」とか思うんです。
だから一般論として、できるだけ最短で終わらせようという意識を持つことがいいのかな、と思います。しかし↓のようなこともあります。
ブログ読みました!博士学位取得した流れも似ていますし、国は同じです😏私は単位取得して日本に帰国し、その7年後に改めて書き始めたので、学会発表や論文審査他渡航費がかかりました💦でも、向こうにいた時には書く気がなかったんですよね💦
— Yukie WATANABE (@puriss5) September 1, 2020
課程が終わってから7年後に書き始めた!そういうこともあるんですね。ですからあくまでも「勢いで」ってのは一般論です。人には様々な事情がありますからね。「勢いじゃなくても終わらせられる」んですね。
最近、以前大学院で一緒だった人が修士を終わらせた、という話を聞きました。多分修士に入って7,8年かかっていると思います。その人がなぜ途中で中断したかというと出産&育児なんですね。女性の場合は年齢的にこれに引っかかることが多いかも知れません。でも7年かかってもちゃんと終わらせられるんですね。
涵養される能力
私は博士課程の際、「家庭」「仕事」「勉強」のバランスをとる中で最も涵養された能力は、上で上げた通り、
・効率性&計画性
の部分だと思っています。どうすればこれを早く終わらせることができるか、子供が熱を出して作業が進まないときに締め切りを守るためにはどうすればいいか、そんなことばかり考えていましたから自然に身につきました。
しかしまあ、それは個人の置かれた状況によって違いますので大学院に行ったからと言って全員が涵養されるわけではないでしょう。
大学院に行って身につくのは当然、その分野の専門性です。
前回の投稿で私は、「大学院に行ったからといって日本語教師としての能力に変化はない」と書きましたが、ちょっとそれは注釈が必要です。
私は日本語教育学を専攻したのではなく、日本語学を専攻したのですね。だからあんまり日本語教師としての能力に変化はなかったのです。しかしもし、大部分の方はそうだと思いますが、日本語教育学を専攻すれば、日本語教師としてのスキルアップにはつながると思います。
僕は修士だけですけど、やっぱり研究したいことがあって院に行ったわけじゃないところは同じですね。とにかく実力不足を何とかしたかったという感じ。
— Yoshifumi Murakami 「ハナキン」の中の人 (@Midogonpapa) August 31, 2020
最近は分野が細分化されていますので、博論を書いたとしてもその他の日本語教育分野のことについては何もしらないということはあろうかと思います。例えば「ピアリーディング」ということをテーマに博論を書いた人が、「シャドーイング」については一般的な知識しかない、ということもありえるでしょう。
しかし大学院ではもちろん授業を受けますし、先輩や同期の研究などを見聞きします。その過程で、いろいろな日本語教育のトレンドに触れられるのは確かです(とは言え、私は経験したことがないのでわかりませんが、おそらくそうでしょう)。結果、日本語教育に関する全般的な知識は増えると思います。
私は日本語学専攻でしたから、文法論とか語彙論とかをよく読みました。特別な専門性としては「程度副詞」にしかありませんが、例えば「自他動詞」の話が出てきたときには「自他ならあの論文を読めばいいだろう」とか、「品詞分類ならまず確かあの人の論考に詳しいのがあったはず」程度のことはわかります。
日本語教育を先行すればそういうレベルのことはわかるから教師としての実力アップにつながるのはおそらく間違いありません。
じっちゃんを泣かせてしまったんですね…院に行って「腐っても論文」を書いてよかったな、と思うのは、学生のレポート・論文指導の時ですかねぇ。
— れいん (@neakkruleng) September 1, 2020
↑こういうのもありますね。文章の書き方は身につきますね。私はそれほど文章はうまくないんですが、論の構成とか、見せ方というの自然と身につきますね。これこれこういう結論を出すにはどのように論じればよいか、ということですね。
だからなのか、学生とか子供が書くのを読んでいると、日本語や国語能力以前の構成のところで疑問が生じます。あと、これは秘密ですけど、妻が何かのコンテストに文章を出した時も添削をしました。私はそれを読んで、「伏線を回収しきれていないなら、その伏線は出さないほうがいい」ということを指摘したんですが、それで一日ケンカしたことを覚えています(笑)。まあ、普通生きていたらまとまった文章書くことってそんなにないですよね。
終わらせることと完成度
何かわかります。
— あり@日本語教育やってます (@jun_arisue) September 1, 2020
僕も同じような気持ちで研究をしています。
一方でそのノリで、ちゃんと博士を取得した佐久間さんは神です 笑。
↑神かどうかは別として(笑)、「ちゃんと終わらせた」ってことには自信を持っています。
これはどういう目的で大学院に行くかとも深く関わるのであれなんですけど、時々「今はまだ書ける自信がない」ということで研究を中断する人がいます。それはその人の問題ですので私は別にそれをどうとも思わないのですが、私に関して言うと自信を持ったことなど一度もないです。
おかしなもので、人の論文って良し悪しがよくわかるんですけど、自分の書いたものって「この理路が正しいのかどうか」「説得力があるのかどうか」よくわからないんですよね。でも私は「良いものを書く」ではなく、「学位をとる」ことが何よりも優先されましたからね。
三谷幸喜の映画で「ラジオの時間」とか、芝居では「ショー・マスト・ゴー・オン」ってのがありますよね。あれの一つのテーマは「終わらせることの価値」です。中身はグダグダでも、終わらせたものには一定の価値がつくんですね。ていうか終わらせないと価値がつかないんですよね。
もちろん「ちゃんとした研究者になりたい」という人は博論や論文が名刺代わりになりますから完成度が「終わらせること」と同様にプライオリティが高くなるのはわかります。
どこが良かったのか
今回ちょっとびっくりしたのが↓のような反応でした。
私にはとても参考になる、ありがたい内容でした!ちょうど、進学しようかどうしようか…とグラグラしていたところだったので、染み入りました。Twitterにあげてくださり、ありがとうございます✨
— 綿あめ (@yezi0110) August 31, 2020
大きな声で言えませんが、私も’なんちゃって’の一人です(といっても博士はこれからですが)。私は研究肌ではないのでやりとおせるか不安ですが、今のままでは身の危険を感じるのでやるしかない、という部分があります。佐久間さんのお話に少し勇気づけられました。
— Madoka Thomas (@MadokaThomas) August 31, 2020
最後が…🤣🤣🤣ラジオの一人語りで聞きたい!🤣
— あひる食堂🏳️🌈その授業、IDで変わります。 (@ahiru5963) August 31, 2020
私は研究興味ないなら大学院行かなくていいんじゃね派で、自身も学士止まりですが、こうしてあっけらかんと開示していただくことで救われる人もいるのかなと感じました。
わたしも大学院に入る前にもっと多くの方の話を聞いておけばよかった…。大学院に興味がある方、ぜひ。 https://t.co/6WnfT0HnnX
— 末松大貴@日本語教育×大学院×振り返り×SNS (@DaikiSuematsu) August 31, 2020
みなさまコメントありがとうございます。
しかし一方、私の前回書いた記事の、どこが「染み入る」「勇気づけられる」「救われる」のかよくわからなかったりします(笑) 私は、単に自分の経験を文章化しただけですし、そこにアドバイスもないし、特別な情報も入っていません。
ただ、近年まれに見るアクセス数を記録したということで、そこそこおもしろく読んでくれたのだな~ということはわかります。やはり「大学院」というのは日本語教師にとって、行くにせよ行かないにせよ、意味深いものなんじゃないかなと思いました。
まとめ
というわけで、私の前回書いた文章への返信やリツイートを中心に、その他補足的なことを書いてきました。
一応注意深く書いたつもりですが、私は皆さまに対し「大学院に行くべきだ」とも「行かないべきだ」とも主張していません。ただ、私の考えたことを書いただけで、そもそも皆さまが大学院に行こうが行くまいが私にはどっちでもいいことです(ということを平気でいうから冷たい男だと言われるんです)。
またこういうことを言うとお叱りをうけるかもしれませんが大事な情報として書いておきます。
私は一応博士を持っているんですが、「大学の教員になりたい!」とか思わない以上、あんまり意味ないんです。日本語教師の仕事は、まあ他の仕事もそうですけど、成果ベースですから学位の有無はあまり関係ありません。
しかしこういうことはあります。
カンボジアに来る時に職場で名刺を作ってもらったんですが、「Ph.Dを入れますか?」って聞かれたんですね。で、ああどうせ使い道のない博士だから、記念に入れてもらおうかなと言って、名刺にPh.Dを入れてもらったんです。
でね、結構名刺の交換をすると反応がいいんですよ。「Ph.D」があるんですね。って感じで。いいか悪いかは別として「肩書」が意味をもつ場合も少なくありません。もちろん肩書よりも実力が重要なのは言うまでもありませんけど、時として肩書だけで判断されてしまうこともありますからね。
まあ、つまり私のようななんちゃって博士はそのくらいしか使いみちがないということの裏返しでもありますね。
今回のつらつら話も何かお役に立てば幸いです。