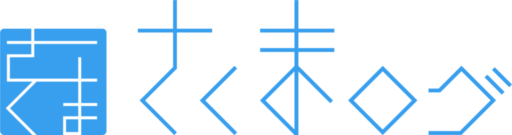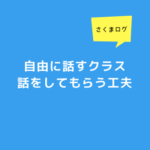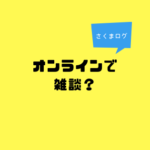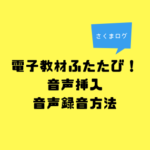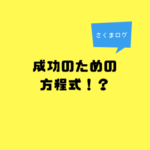10月から職場で新しい授業をスタートさせます。何もないところから90分×20回の授業を設計しました。教科書も手作りです。
教科書の中には聞き取りの部分もあるんですが、当然それも自分たちで録音しなければなりません。
録音したり、動画を撮ったりは今までもしたことがあるのですが、それは私が1人でやる授業でした。今回は所属機関における正式なコースにもなるので、教科書にせよ、音声教材にせよ、ちゃんとしたものを作る必要が出てきました。
今回はその音声教材をどのように作ったかをかんたんに記録しておきます。
どこで録るか
プロの声優を使うとか、そういうことはできません。声を吹き込むのは私の職場のネイティブ講師たちです(私も参加)。
録音専用のスタジオで録るのが最もよいとは思いますが、なかなかそうもいきません。結局教室で撮ることにしました。
Twitter界隈で聞いてみると、いろいろ素晴らしい意見が聞こえてきたのですが、結局はこれなんです↓
こだわると沼。
最初はこだわろうかとも思っていたのですが、方針を変更しました。
ストレスを感じない範囲でベストを尽くす。
というわけで、録音場所は職場の講義室で決定。
何を使って撮るか
手持ちの機器としては「SONYのレコーダー」「ノートパソコン」「スマホ」がありました。
いろいろ検討した結果、職場で貸し出してくれている普段使いのウィンドウズノートパソコンを使うことにしました。
録音ツールも普通のもので、Windows8に付帯しているSOUND RECORDERです↓

・・・っていろいろ書きましたが、特筆すべきものは何もないですね。ごく普通のツールです。ただ、使うマイクはあんまり普通の人は持ってないかも知れません。USB接続のマイクを使いました(↓これと同じ商品ではないですが、似たような値段の商品です)。
数年前にYOUTUBEで動画を量産していた際に購入したものです。なぜUSBマイクにしたかというと、普通の音声入力端子だと「ぶー」っていう雑音が入るんですよね。それが当時は非常に気になり、USBマイクを購入しました。音はクリアで、結構音量も大きくなるので気に入っています。
ただ短所としましては、当然ですけど、USBのとこにしかぶっ込めないことです。例えばスマホにつなぐとかができません。また、今これを書いているChromeBookでも使えませんでした(対応していないのか?)。
どうやって編集するか
さて、次は編集です。ちゃんと録れば、編集は必要ないかも知れませんが、編集をしないことを前提にしますと、一発録りが必須となります。ということは、会話文の最後の最後で笑ってしまったり、間違ってしまったらそれだけで最初から録り直しになってしまいます。
忙しい講師の先生の負担を下げるためにも「間違ってもいいからとりあえず一発で録る」→「後で編集する」ということにしました。
編集に使ったのはこれです。
これの最も良い点は、ブラウザ上で使える!ということです。どうやらChrome限定だという噂もありますが、とにかくソフトをPCにインストールしたりする必要がないのです!!
あんまり専門的な編集はできないと思いますが、切り貼り、複数ファイルのつなぎなどは簡単にできます。しかもできたファイルをGoogleIDと連結させることによって、自動でGoogleドライブに保存してくれるのです!すんごい楽ですよ。
使い方は、ビデオで紹介していますので、ぜひ音声の編集が必要な方はご覧ください(録った音声の切り貼り、効果音の挿入、Googleドライブへの保存の過程がご覧になれます)。
作った後で、なんかこの動画既視感あるな〜と思って調べてみたら、以下に似たような動画がありました。そうそう、忘れていましたが、このブログを見て使い方を覚えていたのでした(笑)。
■「今日の忘備録」redcoolmedia audio editorの 使い方
【学びの牧場】
まあ、でもわざわざ撮った動画をお蔵入りにするのもあれなんで、ここで公開しておきます。
ちなみに、この私の動画はScreencastifyというChromeの拡張機能で撮った動画です。無料だと10分までしか撮れませんが、自動でYoutubeに保存しくれるので超楽ちんです。
まとめ
というわけで、音声教材をどうやって作ったか、について書きました。おそらく「え〜別に普通じゃん」というのがみなさまの印象かもしれません。
はい、そうです。普通なんです。
お金と手間をかければいいものは作れます。例えばプロの音声教材作成会社とかにお願いすれば、クオリティの高いものは作れるでしょう。またそこまでしないにしても、ちょっと高価な機材やスタジオなどを使えば、それなりに良いものが作れます。
ただ、我々は「それだけやっているわけではない」ですよね。ですから何を作るにしても「クオリティ」「手間」「費用」などを全部天秤にかけて考えなければなりません。
今回も天秤にかけて構想を練った結果、このくらいの手間のかけ方で、必要最低限のクオリティのものは作れると踏みました。そして、私は十分使える音声教材ができたと思っています。
というわけで、これが音声教材の正しい作り方ではありませんが、一つの例として受け止めてもらえればいいと思います。