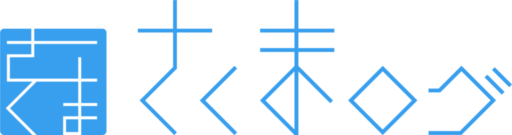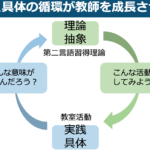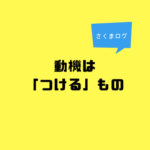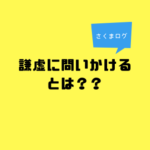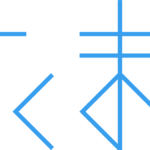今の職場では「まるごと」を主教材とした日本語コースを運営しています。3年間ほど「まるごと」とにらめっこしてきて、いろいろ分かったことがあるのでここに記したいと思います。
結論から言うと、まるごとは
ようできたテキストやな~
ということなんですが、それを以下もう少し解説しましょう。
質を担保してくれる教科書
最近思ったことをツイートしたのが↓です。
最近、自分の授業の質のアベレージが保たれている気がします。
— さくま しろう(佐久間司郎) (@shirogb250) January 6, 2022
それは「まるごと」を使っていることが大きいと思います。とにかく教科書に沿ってやればいいから。
「教科書に沿って」も授業は人によって変わってくるとは思うけど、「アベレージが保てる」というのは大きいんじゃないかなと思います。
以前は、割と授業の出来にばらつきがあったような気がするんですよね。自分の考えた活動がうまくいけば授業もおもしろくなりますが、不発に終わるとお通夜のような授業になる。おそらく日本語教師の方はその感覚わかると思います。
ただ「まるごと」を使い始めてからはそれが減って、割と浮き沈みのない授業ができているとおもうんですよ。それが「まるごと」の利点の一つだと思います。
というのはですね、この教科書が、練習や必要な素材を提供してくれており、教科書の順序に沿って学習を進めていけば、教科書として目標としてる行動ができるようになるという構成になっているからです。
…まあ理屈はわかると思いますが、特に私のような旧時代の教師は一瞬戸惑いが出るんですよね。
教科書をなぞるだけでいいのか?
って。私もそんなに旧時代の年代ではないんですけど(デビュー2004年)、日本語の授業って、導入をしっかりやって、わかりやすい例文を提示して、多方面から練習できる教材を集めてきて、ハンドアウトを作って…っていうのが「あるべき姿」だったんですね。教科書を最初から最後までなぞっていくような授業をしようもんなら「手を抜いている」「教科書を教えるんじゃない、教科書で教えるんだ」などと叱責を受けたものでした。
でもね、「まるごと」を使っていて思うのは、変に余計なものを入れない方がいいということなんですよね。重複しますけど、この教科書は、提示された手順に沿ってやると、目標が達成されるようにできているんですよ。だから、とにかく教科書をなぞればよい。余計なものを入れてもいいかもしれないけど、そもそも教科書作成の時点でかなり吟味されているから、下手に素人考えでいろいろ入れない方がいい。
もちろん、能力のすごく高い教師であれば、「例文一つ」「行動目標一つ」与えても素晴らしい準備をし、素晴らしい授業ができるかもしれません。でも、そんな教師はごく一握りです。できる人はそうすればいい。
「まるごと」のように「教科書通りにすすめればいいっす」というやり方は、能力にバラつきのある世界各国の日本語授業レベルのアベレージをある程度均一に整えることができるということで、大衆的な教育の本質をしっかりとついたものと言えます。
新人でも扱いやすい
そもそも教師って、誰でもなれないといけないもんなんですよね。って言ったら袋叩きにあうかもしれませんけど、袋を出すまえに私の話を聞いてください。
学校の先生って日本全国に何人いるか知っていますか?私も知りませんけど、数十万はいるとおもいます。その全ての先生が卓越した能力を持っているでしょうか?もちろん教員免許を取るなどの要件はありますが、素晴らしく高い能力を持った人だけができる仕事ではありません。普通の人ができる仕事です。というか、凡庸な能力の教員ばかりでも、ある程度の質を保った教育をしなければなりません。そのため教科書やカリキュラムとかが決められているわけですね(もちろんそれでも能力差は出ますが)。
もし「素晴らしく卓越した能力を持った教員でなければ教育が成り立たない」というのであれば日本などとっくの昔に滅んでいます。
日本語教育も同じではないでしょうか。一定の教育を受けて一定の要件を満たせばだれでも日本語教師になれます。そしてさっきの議論と同じで、素晴らしく卓越した能力をもった日本語教師でなければ教育が成り立たないというのではだめなんですよね。もちろん、一人一人の教師は自分の能力の開花のために努力すべきですけど、少し能力のある人や業界全体を見渡せる人は「業界や地域全体の授業の質のアベレージをどうあげていくか」を考えていく必要があります。
その結果の一つが「まるごと」なんじゃないかな、と思っています。
一つ卑近な例を出しますと、私の職場には業界未経験で日本語教師として採用される人が少なくありません。その中で、今まで見た全ての人は未経験でも即戦力として活躍されています。最初は戸惑いがあっても、何度かフィードバックをおこなううちに、すぐにそれなりの授業ができるようになっています。そして大体、経験十数年の私よりみなさん授業がうまいです。正直な話。
もちろん採用に至るまでには選別の過程がありますし、授業が上手にできているのはその人たちの能力に帰する面も多いと思うのですが、使っているのが「まるごと」であるというのは一つの要素だと思っています。最初の研修では「とにかく教科書に沿ってやってください」と伝えています。
第二言語習得理論をしっかりと踏まえている
それと、最近第二言語習得理論の本を読んでいて思うんですが、おもしろいほどに「まるごと」はそれに合致しているんですよね。もうグルなんじゃないかっていうくらいに(笑)
いや冗談ですよ。グルなんじゃなくて、「まるごと」がしっかりと第二言語習得理論に基づいて作られているからそうなっているんですよね。実際「まるごと」ウェブページに↓のように書かれていますね。
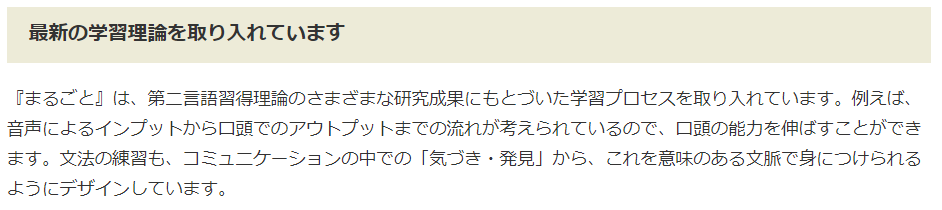
だから、教科書に沿って授業をおこなうことによって、同時に「効率の良い学び」を実現することにもつながるわけですね。だからこそ、「教科書に沿ってやるべし」ということなのですよね。
量の多さと内容の充実は諸刃の剣
と、ここまで「まるごと」礼賛の内容だったわけですが、当然デメリットも存在します。それも紹介しておかないとフェアじゃないですよね。
まず一点目。量が多くなるということ。
「教科書に沿ってやっていればOK」ということは、教科書に練習問題なりなんなりが豊富に入っているということです。ということは教科書が分厚くなるということにもなります。「初級2」で初級が終わりと考えた場合、そこまでに6冊の本を要します(かつどう、りかいを両方使った場合)。またそれはコスト増にもつながりますね。6冊買うとしたら1万円を超えますね。
まあこれは諸刃の剣ですよね。内容が充実すればするほど本体が大きくなってしまうというのはしょうがありませんかね。
あとは…特にありませんかね。デメリットは。
まとめ
というわけで「まるごと」について書いてきました。
・順序に沿ってやればいいだけだから楽
・それでいてちゃんと習得につながる
というわけで、「まるごと」は非常に良いテキストだと思っています。
ただし、一応書いておきますが、ここでの話は「まるごと」の使用が学習者の学習目的に合致していることが前提になっています。基本的に「まるごと」が対象として想定しているのは「海外で日本語を学ぶ」「特定の目的(労働者として日本に行くとか)ではない」「成人」だと思いますが、そうでない人にとっては効果的ではないかもしれません。
また、「教科書に沿ってやればいい」と言っても、「音声をどのように聞かせるか」「どのように読解部分をおこなうか」「会話練習をどのようにおこなうか」についてはいちいち指示が出されているわけではありませんので、そのあたりは工夫や経験が必要になる部分もあります。
授業の準備にしても、楽と言えば楽ですが、「ネイティブなら初見で授業ができる」というものではありません。私の場合、90分の授業をおこなうのにそれと同じくらいの時間は準備に投じていると思います(もちろんこれは他の業務との兼ね合いもありますが)。
と、なんだかエクスキューズが続いて歯切れが悪いですが、とにかく「まるごと」を一定期間使って最近思うことを書いてみました。